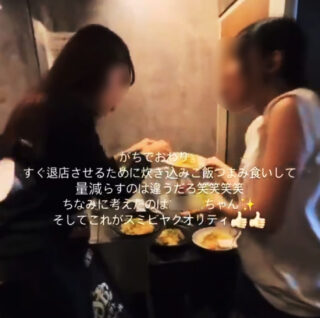2025年10月、高市早苗氏が日本の新たなリーダーとして国際舞台にデビューし、その英語力に、かつてないほどの熱い視線が注がれています。総理大臣就任直後、マレーシアで開催されたASEAN(東南アジア諸国連合)関連会議で見せた英語スピーチは、瞬く間に国内外で話題となりました。「凄い」という称賛の声が上がる一方で、「ネイティブとはほど遠い」といった冷静な意見も聞かれ、評価は真っ二つに割れている印象です。
実際のところ、高市早苗総理の英語力はどの程度のレベルなのでしょうか。「ペラペラ」なのでしょうか、それとも「実務レベル」なのでしょうか。また、そもそもなぜ英語を話すことができるのか、その背景にある知られざる経歴も気になるところです。
さらに、多くの人の記憶に新しいのが、2025年の自民党総裁選のさなかに繰り広げられた、ひろゆき(西村博之)氏とのあのやり取りです。「英語で答えて」という鋭い要求に対し、高市氏は当時どのように対応したのか。あの場面が、現在の英語力評価にどう影響しているのかも見逃せません。
この記事では、高市早苗氏の英語力に関するあらゆる角度からの疑問に答えるため、公開されている情報や専門家のコメントを徹底的にリサーチし、深掘り分析しました。
- 専門家による客観的評価:ASEANでのスピーチは「凄い」のか?「うまくない」のか?
- 英語力のレベル:「ペラペラ」には見えないが、実際どのくらい話せるのか?
- 習得の背景:なぜ英語を話せる?その理由となった「米国議会フェロー」とは何者か?
- ひろゆき氏との応酬:あの「英語で回答して」要求に、本当はどう対応したのか?
- 歴代総理との比較:日本のリーダーとして、英語力はどれほど重要なのか?
- 世論の反応:ネット上で渦巻く賛否両論の意見を徹底分析。
本記事を最後までお読みいただくことで、高市早苗氏の英語力に関する多角的な事実と、その評価の背景にある日本社会の複雑な視点まで、深くご理解いただけることでしょう。
1. 高市早苗の英語力が話題?英語力は凄いのか?
高市早苗氏の英語力がこれほどまでにクローズアップされた直接のきっかけは、2025年10月26日、総理大臣として初参加したマレーシアでのASEAN関連会議でした。この国際的な檜舞台で、高市氏は自ら英語でスピーチを行いました。この「外交デビュー」が、専門家やメディア、そしてネットユーザーの間で大きな議論を巻き起こすこととなったのです。
1-1. 専門家によるスピーチ評価:「うまくない」が「好感が持てる」
まず、このスピーチを専門家はどう見たのでしょうか。2025年10月26日放送のフジテレビ系「Mr.サンデー」では、アメリカ人の経済アナリストであるジョセフ・クラフト氏が、このスピーチについて非常に興味深いコメントをしています。
クラフト氏は、まず技術的な流暢さについて、「正直、言うとそんなにうまくないんですが」と率直に評価しました。これは、いわゆる「ネイティブスピーカー」や「ペラペラ」といったレベルではないことを示しています。日本国内では「総理の英語」として期待値が上がっていただけに、このストレートな評価は的を射ていると言えるかもしれません。
しかし、クラフト氏の評価はそこで終わりませんでした。彼は続けて、「物怖じせず英語をしゃべる姿勢はすごく好感が持てる」と、その態度を高く評価したのです。通訳に頼らず、自らの言葉で、たとえ流暢ではなくとも堂々と発信しようとする姿勢。これこそが、外交の場において「好感」を持たれる重要な要素であると指摘しています。言語の壁を恐れないコミュニケーション意欲の高さが、ポジティブなイメージを与えたようです。
さらにクラフト氏は、「あと、しゃべり方がトランプに似ていると僕は思う」という、非常にユニークな分析を加えました。これにはスタジオも「へぇ~!」と驚きの声を上げました。この「似ている」という点が、発音のイントネーションを指すのか、あるいは聴衆に直接的かつシンプルに訴えかけるようなスピーチのスタイル(デリバリー)を指すのかは定かではありません。しかし、トランプ前大統領もまた、伝統的なエリート層の英語とは異なる、独特で力強い話し方で支持を集めた人物です。高市氏のスピーチにも、そのような「伝える力」の片鱗が見えたのかもしれません。
1-2. 須賀川拓氏の評価:「ペラペラではない」が「ものすごく努力された」
もう一人、ジャーナリストの視点から鋭い分析を加えたのが、ウクライナやガザ地区など世界の紛争地帯を取材してきた戦場ジャーナリストの須賀川拓氏です。須賀川氏は2025年10月27日、自身のX(旧ツイッター)で高市氏のスピーチについて言及しました。
須賀川氏もまた、「英語ネイティブの視点から見たら、決してペラペラではない」と、クラフト氏と同様に流暢さについては冷静な評価を下しています。この点で、専門家の見解は一致していると言えるでしょう。
しかし、須賀川氏が注目したのは「現在のレベル」だけではありませんでした。彼は、「でも、以前の動画と比べて、ものすごく努力されたのだなと感じます」と述べ、過去の姿(例えば閣僚時代のスピーチなど)と比較した上での「成長」と「努力の跡」を明確に指摘しました。これは、単なる一時点での評価ではなく、プロセスを重視するジャーナリストならではの視点です。
須賀川氏はさらに、言語能力そのものよりも「伝える力」こそが核心であると説いています。彼のポストは非常に示唆に富むものでした。
「色々な現場を見てきたけど、言語能力があっても伝わらない人もいる。この、『伝える力』を英語では『delivery(デリバリー)』と言います。発音が全てでは、決してありません。高市総理を必要以上に持ち上げる必要はないし、むしろその努力に敬意を持つべきだと思います」
ここで言う「delivery」とは、単に言葉を「配達」することではありません。声のトーン、表情、間の取り方、そして何よりも「伝えたい」という熱意や意志を含めた、総合的な「伝達力」を指します。須賀川氏は、紛争地という極限の状況で、言葉の壁を超えて人々の思いを伝えてきた経験から、この「delivery」の重要性を痛感しているのでしょう。高市氏のスピーチに、その片鱗を感じ取ったのかもしれません。
1-3. 結論:「凄い」のは流暢さではなく「姿勢」と「努力」
これらの専門家の意見を総合すると、高市早苗氏の英語力に対する評価の核心が見えてきます。
彼女の英語力は、技術的な流暢さ、すなわち「ペラペラ」かどうかという尺度で測れば、「凄い」レベルには達していない可能性が高いです。これは、専門家二人が共通して指摘している点です。
しかし、高市氏の「凄さ」は別の次元にあります。それは、
- 物怖じしない「姿勢」:国際会議という大舞台で、完璧ではない英語でも堂々と発信しようとする勇気。(クラフト氏の評価)
- 継続的な「努力」:過去の自分と比較して、明らかに上達が見られる、その学習プロセス。(須賀川氏の評価)
- 伝える力「Delivery」:発音の正確さ以上に、メッセージを届けようとする意志。(須賀川氏の評価)
つまり、高市氏の英語力は、単なる「スキル(技能)」として「凄い」のではなく、彼女の政治家としての「スタンス(姿勢)」や「プロセス(努力)」において、多くの人が「好感が持てる」「敬意を持つべき」と感じる要素を含んでいると言えます。日本国内で「発音が完璧でないと恥ずかしい」と考えがちな英語コンプレックスを打ち破るような、その堂々とした態度こそが、ある種の人々にとっては「凄い」と映っているのではないでしょうか。
2. 高市早苗は英語をどのくらい話せる?ペラペラではない?
専門家の間でも「うまくないが好感が持てる」「努力に敬意を持つべき」と評価が分かれる高市早苗氏の英語力。では、客観的に見て、彼女は「どのくらい」英語を話せるのでしょうか。「ペラペラ」というイメージとは異なる、その実務的な能力について深く掘り下げていきます。
2-1. 準備されたスピーチは英語で対応可能
まず明確な事実として、高市氏は「準備された原稿がある」公的な場面においては、英語でスピーチを行う能力を有しています。これは、今回のASEAN関連会議のスピーチが初めてではありません。彼女のキャリアを通じて、重要な国際会議で英語での発信を試みてきた実績が確認されています。
例えば、閣僚時代には以下のような実績があります。
- 宇宙の持続可能性サミット(2024年):この国際会議において、高市氏は開会セッションで英語による挨拶(Remarks)を行っています。宇宙政策という高度に専門的な分野において、国際的な共通言語である英語で日本の立場を説明する役割を果たしました。
- IAEA(国際原子力機関)総会(過去):原子力政策という、これもまた専門性と正確性が極めて高く求められる分野の国際会議であるIAEA総会においても、高市氏は英語でのステートメント(声明)を発表した経歴を持っています。
これらの実績が示すのは、彼女の英語力が「付け焼き刃」ではないということです。特に、ASEANでのスピーチでは、単に原稿を読み上げるだけでなく、時折、聴衆に視線を送るなど、「伝える」意識(デリバリー)も持って臨んでいた様子がうかがえました。これは、事前に相当な練習と準備を積んできたことの表れでしょう。
現代の政治リーダーにとって、国際会議の場でスクリプト(原稿)に基づいて英語でスピーチを行うことは、もはや「凄い」特殊能力というよりも、「必須の業務スキル」の一つです。高市氏がこの業務を(たとえ発音に課題があるとしても)着実に実行している点は、彼女の政治家としての実務能力と、国際舞台に対する真摯な姿勢を示していると言えます。
2-2. 即興の質疑応答(Q&A)は日本語を選択する傾向
一方で、高市氏の英語力は「万能」ではないことも、公の場での対応から明らかになっています。特に、「原稿のない」即興での英語対応、とりわけ長文での議論や質疑応答(Q&A)については、慎重な姿勢を見せるか、あるいは日本語を選択する傾向が顕著です。
この傾向を最も象徴的に示したのが、2025年の自民党総裁選の最中に行われたネット討論会での一幕でした(この詳細は第4章で詳述します)。この時、コメンテーターのひろゆき氏から「英語で答えて」と即興での対応を強く求められた高市氏は、流暢な英語で政策を長々と語ることはしませんでした。
彼女の取った行動は、“Japan is back.”(日本は戻ってきた) という、非常に短く象徴的な英語フレーズをまず口にすることでした。しかし、その後の政策の具体的な説明や議論の「本論」に入ると、即座に日本語に切り替え、自身の考えを詳細に述べたのです。
この対応から、二つの可能性が推測できます。
- 技術的な限界:即興で、複雑な政治的・経済的な概念を、誤解なく英語で論理的に組み立てて反論する(いわゆる「ペラペラ」なディベート能力)については、高市氏自身が十分な自信を持っていない可能性。
- 戦略的な判断:あるいは、これは彼女の政治家としての「戦略」かもしれません。総裁選という国のリーダーを決める重要な討論の場で、万が一にも英語のニュアンスを間違えて失言と捉えられたり、政策の意図が不正確に伝わったりするリスクを冒すことはできない。そう判断し、あえて最も正確かつ雄弁に語れる母国語(日本語)を選択したという見方です。
どちらにせよ、このエピソードは、高市氏が準備されたスピーチはこなせる一方で、即興の英語ディベートは(少なくとも公の場では)積極的に行わないスタイルであることを示しています。
2-3. 総合評価:「ペラペラ」ではなく「実務的な場面対応型」
これら二つの側面、「準備されたスピーチはOK」と「即興の議論は日本語優先」を総合すると、高市早苗氏の英語力は「どのくらい話せるか?」という問いに対する、より正確な答えが見えてきます。
結論として、彼女の英語力は「ネイティブのようにペラペラと、どんな場面でも自由自在に会話や議論ができるレベル」ではありません。
その代わり、彼女の能力は「実務的な場面対応型」と呼ぶのが最も適切でしょう。これは、日常会話の流暢さや、ウィットに富んだジョークを交わす能力とは異なります。そうではなく、「国際会議での公式挨拶」「準備された声明の発表」といった、政治家としての「公務」や「実務」で必要とされる特定の場面において、その役割を果たすために最適化された英語力である、と分析できます。
彼女にとって英語は、コミュニケーションを楽しむためのものではなく、政治的なメッセージを国際社会に向けて発信するための「ツール(道具)」としての側面が強いのかもしれません。そのツールを、彼女は最も安全かつ効果的な「準備されたスピーチ」という形で使用することを選択しているのです。
3. 高市早苗が英語を話せる理由はなぜなのか?
高市氏が、たとえ「場面対応型」であっても、専門的な内容を含む英語スピーチをこなせるのはなぜでしょうか。多くの人が想像するような「有名大学への留学経験」や「幼少期の海外生活」といった華々しい経歴は、彼女のプロフィールには見当たりません。しかし、彼女の英語力の基盤となっているのは、それら以上に実践的で、非常にユニークな20代の経験です。
3-1. 理由は「米国連邦議会フェロー」としての実務経験
高市氏の英語力の最大の理由は、彼女の公式プロフィール(首相官邸ホームページなどにも記載)にある「U.S. Congressional Fellow(米国連邦議会フェロー)」という経歴にあります。
これは、彼女が神戸大学を卒業し、松下政経塾を経た後の1987年(当時20代半ば)に経験したものです。この「フェロー」という言葉から、単なる「研究員」や「留学生」を想像するかもしれませんが、その実態は大きく異なります。
このプログラムは、米国の政治の中枢であるワシントンD.C.の連邦議会に文字通り「入り込み」、実際に議員のスタッフ(補佐官)の一員として働くという、極めてハードな実務研修プログラムなのです。
高市氏はここで、政策立案の最前線に身を置きました。彼女の日常業務は、カフェで英会話のレッスンを受けるような生易しいものではなく、
- 膨大な量の政策文書や法案を英語で読み込む(リーディング)
- 政策に関するリサーチを行い、レポートやメモを英語で作成する(ライティング)
- 議会の公聴会やブリーフィングに出席し、議論を聞き取る(リスニング)
- 上司である議員や他のスタッフと、業務上の議論や報告を行う(スピーキング)
といった、すべてが英語で行われるプロフェッショナルな実務環境でした。これこそが、「なぜ高市早苗は英語を話せるのか」という問いに対する、最も直接的かつ強力な答えです。
3-2. 「実務英語」のバックグラウンドが形作るスピーチスタイル
この「米国連邦議会フェロー」という特異な経歴は、前章で分析した高市氏の英語スタイル(準備スピーチは得意だが、即興は苦手かもしれない)の理由をも、明確に説明してくれます。
考えてみてください。議会での業務で最も重要視されるのは、「流暢な雑談」よりも、「正確な政策理解」と「論理的な報告」です。彼女が日常的に触れていたのは、日常会話の英語(スラングやジョーク)ではなく、法案や公文書で使われる、硬く、専門的で、論理的な「実務英語(プロフェッショナル・イングリッシュ)」だったのです。
このため、彼女の英語力は以下の点で強みが形成されたと考えられます。
- 強み:専門用語やフォーマルな表現を多用する、準備された原稿(スピーチ、声明)の読解と発表。
- (相対的な)弱み:原稿がなく、即座のウィットや反応が求められる、カジュアルな会話や即興ディベート。
高市氏の英語は、「留学で身につけた流暢な英語」ではなく、「ワシントンの実務現場で鍛え上げられた、政策志向の英語」なのです。このバックグラウンドは、単に「英語が話せる」政治家というよりも、政治の現場で言語をどう使うかを学んできた、より専門的なスキルセットを示唆しています。
3-3. 継続的な努力と学習の軌跡
ただし、彼女の英語力が1980年代の経験だけで止まっているわけではないことも、指摘しておく必要があります。ジャーナリストの須賀川拓氏が「ものすごく努力されたのだなと感じます」と述べたように、過去の経験にあぐらをかくことなく、現在の立場(総理大臣)として必要な準備を怠っていないことがうかがえます。
1980年代に培った「実務英語」の基礎(土台)の上に、総理大臣として発信すべきメッセージ(ASEANでのスピーチ内容など)を載せ、それを国際社会に届けるために、発音や「delivery(伝える力)」を現在進行形で猛練習している。これが、高市氏の英語力の全容である可能性が最も高いでしょう。
彼女の英語力は、過去の遺産であると同時に、現在の「継続的な努力」の産物でもあるのです。この姿勢こそが、専門家が「好感」「敬意」と評した部分と重なります。
4. 高市早苗はひろゆきに英語で回答をしてと言われどうした?
高市氏の英語力を語る上で、避けて通れないのが、2025年の自民党総裁選ネット討論会での「ひろゆき氏との対決」です。この一件は、彼女の英語力の実態だけでなく、政治家としての「瞬発力」や「危機管理能力」をも浮き彫りにしました。
4-1. 2025年自民党総裁選ネット討論会での「無茶振り」
その場面は、2025年に行われた自民党総裁選のネット討論会(ABEMA/テレ朝NEWSなどで配信)で訪れました。総裁選という、一国のリーダーを決める真剣な政策討論の場。そのコメンテーターとして登場したのが、西村博之(ひろゆき)氏でした。
ひろゆき氏は、候補者であった高市氏に対し、政策に関する議論の最中、突如として「英語で答えられます?」と質問を投げかけました。これは、単なる語学力のテストを超えた、高市氏の対応力や動揺を試すかのような、非常にトリッキーな「無茶振り」でした。
生放送の討論会、多くの国民が見守る中、他の候補者もいる前で、高市氏がどう対応するかに一瞬で注目が集まりました。
4-2. 高市氏の対応:”Japan is back.”という象徴的フレーズ
この予期せぬ奇襲に対し、高市氏は動揺した様子を見せることなく、即座に次のような対応を取りました。
まず、ひろゆき氏の要求(英語で)に応じる形で、“Japan is back.”(日本は戻ってきた)と、短くも力強い英語のフレーズを明瞭に発しました。
この “Japan is back.” という言葉は、単なる英語の挨拶ではありません。これは、安倍晋三元総理が国際舞台で多用し、日本の国際社会への復帰を強くアピールした、非常に政治的なメッセージ性を持つ「キラーフレーズ」です。高市氏が安倍氏の政治信条の継承を掲げていたことを考えれば、これは瞬時に計算された、最も効果的な「英語での回答」だったと言えます。
しかし、彼女はそこで終わりませんでした。この象徴的なフレーズを述べた直後、即座に日本語に切り替え、ひろゆき氏が求めた政策の本論について、よどみなく詳細な説明を始めたのです。
4-3. なぜ日本語で本論を回答したのか?その戦略的意図
この一連の対応(英語ワンフレーズ + 日本語での本論)は、高市氏の極めて高度な「戦略的判断」と「政治的センス」を示しています。なぜ彼女は即興の英語議論に乗らなかったのでしょうか。
- リスク回避(守り):
最大の理由は「リスク回避」です。総裁選というコンマ1秒の失言が命取りになる場で、不慣れな即興英語で政策を語ることは、計り知れないリスクを伴います。言葉のニュアンスを間違えれば、メディアやライバル陣営から「政策理解が浅い」「外交不安」と格好の攻撃材料を与えてしまいます。彼女は、そのリスクを瞬時に判断し、回避しました。 - 正確な伝達(攻め):
彼女がアピールすべき相手は、ひろゆき氏一人ではありません。その先にいる、討論会を見ている「日本の有権者」や「自民党員」です。彼らに対し、自身の複雑な政策理念を最も正確に、最も情熱的に伝えることができる言語は、間違いなく日本語です。彼女は、メディアの挑発に乗る(英語で答える)ことよりも、有権者に正確に訴えかける(日本語で答える)という「本質」を選んだのです。 - 「対応した」という事実(カウンター):
もし彼女が完全に日本語だけで答えていたら、「ひろゆき氏の要求を無視した」「英語から逃げた」と批判されたかもしれません。しかし、彼女は最初に “Japan is back.” という「英語での回答」を意図的に入れています。これにより、「要求には応えた(無視していない)」という事実を作りつつ、議論の主導権を即座に自分の得意な日本語の土俵に引き戻したのです。
この対応は、彼女の英語力が「ペラペラ」ではないことを示唆すると同時に、それ以上に、彼女がメディアの「無茶振り」を冷静にさばき、政治的リスクを最小限に抑えつつ、自身の主張を最大限に伝えるという、極めて老練な「政治家としての危機管理能力」を持っていることを証明した場面だったと言えるでしょう。
4-4. 他の候補者との比較:対応が分かれた理由
この「ひろゆき氏の英語質問」は、高市氏だけでなく、他の候補者にも向けられました。そして、その対応は見事に分かれました。
- 英語で回答した候補者:
林芳正氏(現官房長官)や茂木敏充氏などは、ひろゆき氏の要求に応じ、流暢な英語で政策を説明しました。特に林氏はハーバード大学大学院卒であり、田崎史郎氏が「(林氏は)すごいですけど」と評する通り、別格の英語力を持ちます。彼らにとって英語で答えることは、自らの「国際感覚」をアピールする絶好の機会でした。 - 日本語で回答した候補者:
一方で、高市氏と同様に、即興の英語対応を避け、日本語での回答を選択した候補者もいました。
この比較からわかることは、総裁選という場において、「高い英語力」は強力なアピールポイント(武器)にはなるものの、それが「必須条件」ではないということです。高市氏の取った「ワンフレーズ英語 + 日本語本論」という対応は、英語が「超得意」ではない候補者として、政治的ダメージを最小限に抑え、かつ自身のメッセージ性を(”Japan is back.”に込めて)発信するという、非常にクレバーな「最適解」だったと分析できます。
5. 総理大臣の英語力の重要性とは?過去の総理大臣で英語がペラペラなのは誰?
高市早苗氏の英語力がこれほどまでに注目を集める背景には、「日本の総理大臣にとって、英語力はどれほど重要な資質なのか?」という、長年にわたる国民的な問いが存在します。国際会議が日常化し、首脳同士の直接対話が外交成果を左右する現代において、英語力は単なる「教養」から「戦略的ツール」へとその意味合いを変えつつあります。
高市氏の英語力が「強い」と評される一方で、歴代の総理大臣たちはこの課題とどう向き合ってきたのでしょうか。過去の事例と比較しながら、その重要性を深く掘り下げます。
5-1. 総理大臣の英語力は「外交の武器」か?「必須スキル」か?
まず、総理大臣の英語力は「必須スキル」かと問われれば、答えは「ノー」でしょう。なぜなら、最も重要な首脳会談や公式な国際会議の場では、必ず同時通訳が介在するからです。外交交渉は、一言一句のニュアンスが国益に直結する極めてデリケートな作業です。自らの英語力に頼るあまり、意図しない誤解や「失言」を招くリスクを冒すことはできません。そのため、プロフェッショナルの通訳を介して、自らの意思を100%正確に伝えることが、外交の鉄則とされています。
しかし、「必須ではない」からといって「不要」ということにはなりません。政治ジャーナリストの田崎史郎氏は、2025年10月27日放送のTBS系「ひるおび!」において、高市氏のASEANでの外交デビューを評し、「やっぱり、英語がしゃべれるっていうのは強いですよね」と断言しています。この「強さ」こそが、英語力の核心です。
では、何が「強い」のでしょうか。それは、公式会談の前後や晩餐会、あるいは廊下での「立ち話」といった、通訳を介さないインフォーマルな場面でのコミュニケーション能力です。首脳同士が直接雑談を交わし、個人的な信頼関係(ラポール)を築くこと。これこそが、公式会談の「本音」を引き出し、交渉を円滑に進める上での強力な「外交の武器(加点要素)」となります。
また、戦場ジャーナリストの須賀川拓氏が指摘した「delivery(伝える力)」も重要です。たとえ通訳を介すスピーチであっても、自らが英語のニュアンスを理解していれば、聴衆の反応を見ながら「間」を調整したり、強調するポイントを変えたりすることができます。高市氏が「物怖じせず」英語を話す姿勢を見せること自体が、相手国に対し「私たちはあなた方と直接コミュニケーションを取りたい」というポジティブなメッセージとなり得るのです。
5-2. 過去の「英語が堪能」と評された総理大臣たち
高市氏の英語力が話題になる中で、比較対象として名前が挙がるのが、過去に高い英語力を披露してきた総理大臣たちです。田崎史郎氏が「男性の総理大臣だと、うまくしゃべれる人って、そんなにいない」と指摘した通り、全員が堪能だったわけではありませんが、特筆すべき人物は確かに存在します。
岸田文雄 氏(前総理大臣)
近年の総理として、その英語力が高く評価された筆頭格です。2024年4月には、米国の連邦議会合同会議において、全編英語による歴史的な演説を行いました。単に原稿を読むだけでなく、ジョークを交えて議場の笑いを誘い、スタンディングオベーションを受けるなど、英語を完全に「使いこなし」て米国の議員たちの心を掴んだ姿は、多くの国民の記憶に新しいところです。
安倍晋三 氏(元総理大臣)
安倍氏もまた、2015年4月に米連邦議会合同会議で「希望の同盟へ」と題した英語演説を行っています。高市氏が今回(ひろゆき氏への回答で)使用した “Japan is back.” というフレーズも、元は安倍氏が国際舞台で日本の復活をアピールするために用いたものです。安倍氏は、特にトランプ前大統領との間では通訳を介さずゴルフカートで直接対話するなど、首脳同士の「個人的な信頼関係」の構築に英語を最大限に活用した好例と言えます。
麻生太郎 氏(元総理大臣)
政界きっての英語堪能者として知られています。米国(スタンフォード大学大学院)や英国(ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス)への留学経験を持ち、その経歴に裏打ちされた流暢な英語は、閣僚時代から数々の英語での講演動画が残されていることからも明らかです。
林芳正 氏(現官房長官・元外務大臣)
田崎史郎氏が「林芳正はすごいですけど」と、例外中の例外として名前を挙げたのが林氏です。ハーバード大学大学院卒という経歴を持ち、その英語力はネイティブスピーカーと遜色ないレベルと評されています。高市氏が総裁選を争ったライバルの一人でもあり、その英語力は比較対象とされやすい存在です。2025年の総裁選ネット討論会でも、ひろゆき氏の要求に対し、流暢な英語で即座に回答していました。
5-3. 田崎史郎氏が指摘する「男性総理」の英語力の実情
田崎史郎氏による「男性の総理大臣だと、うまくしゃべれる人って、そんなにいないんですよ」という指摘は、日本の政治における一つの現実を示しています。もちろん、前述の安倍氏や麻生氏のような例外はいますが、戦後の歴代総理全体を見渡せば、国際舞台での英語コミュニケーションを得意としていたリーダーは少数派でした。
この文脈の中で、高市早苗氏は二重の意味で目立つ存在となります。一つは、田崎氏が指摘した「英語をうまく話せる人が少ない」という集団の中で、少なくとも「物怖じせずに英語でスピーチをしようとする」総理であること。もう一つは、彼女が日本初の「女性総理」であることです。
田崎氏が「彼女の強みを遺憾なく発揮している」と評したのは、この希少性ゆえでしょう。高市氏が(たとえ技術的には発展途上であっても)英語での発信を続ける姿勢は、従来の日本のリーダー像とは異なる新しい姿を国際社会に示すことになり、それ自体が「強い」メッセージとなり得るのです。
6. 高市早苗の英語力に対するネット上の反応とは?
高市早苗氏の英語スピーチが報じられると、インターネット上、特にYahoo!ニュースのコメント欄などでは、国民から非常に多くの、そして熱量の高い反応が寄せられました。驚くべきことに、その多くは「発音が悪い」といった批判的なものではなく、彼女の姿勢を支持し、称賛する声でした。
専門家の評価(「うまくないが好感が持てる」「努力に敬意」)と、国民の受け止め方には、奇妙なほどの一致が見られます。なぜ多くの人々は、技術的な流暢さよりも、彼女の「心」を評価したのでしょうか。その多様な意見を分類し、深層心理を分析します。
6-1. 「発音より努力」高市総理の姿勢を評価する声
最も多く見られたのが、彼女の英語の「結果(流暢さ)」ではなく、「プロセス(努力)」や「背景(状況)」に焦点を当てた意見です。
ネット上では、「年齢とともに記憶力も体力も落ちます。その中で学び、激務をこなし、旦那様の介護までされているとか。…努力家で優秀な方だと思います」といったコメントに象徴されるように、高市氏の個人的な背景や年齢を考慮し、その上で学習を続ける姿勢そのものを称賛する声が目立ちました。
また、「普通なら退職する年齢で日本と世界に立ち向かう高市さんの気概に感動しました」という意見や、「生き様で他人を感化できるのはすごいこと」といった、彼女の政治家としての「気概」や「生き様」にまで言及するコメントも多く、単なる語学力の評価を超えた、人物評価の域に達していることがうかがえます。
さらに、「自分もはるか昔に留学してたけど使わないと忘れちゃうんよ。…勉強し直せば思い出してくるから高市さんも努力してると思います」という共感の声もありました。これは、英語学習の難しさ(特に一度離れてからの学び直し)を実感している人々からの、現実的なエールと言えるでしょう。
6-2. 「伝える力」こそが本質。「ド根性英語」を支持する意見
次に多かったのが、「英語はツール(道具)に過ぎない」という、コミュニケーションの本質に迫る意見です。「言語の1番は『気持ちを伝える事』発音が日本語英語でも意味が伝わればそれで良いんです」というコメントは、この考え方を端的に表しています。
実際に海外での実務経験があるという人物からは、「私は20年以上海外で仕事をしていました。高市さんの英語スピーチを聞きましたが話の内容が英語で理解出来ており、訴えが相手に伝わる英語スピーチだと思いました」と、プロの視点からも「伝わっている」というお墨付きが与えられています。
この「伝える意志」を称賛する声は、やがて「ド根性英語」というユニークな表現を生み出しました。「伝えようという強い思いを持ち必死で言葉にしようとしています。相手の心を揺さぶるのはこうしたド根性英語です」というコメントです。完璧な発音でクールに話す英語よりも、拙くとも熱意を持って必死に伝えようとする「ド根性」の方が、人の心を動かすのだという、非常に日本的な価値観が反映された評価と言えます。
6-3. グローバルスタンダードの視点:ネイティブである必要はない
「ド根性」という精神論だけでなく、よりグローバルな視点から高市氏の英語を擁護する意見も強力でした。
「日本人が英語が苦手な理由の一つです。発音がネイティブでなければダサい、話せる事にならないという風潮です」と、まず日本の「発音至上主義」に疑問を呈する声が上がりました。そして、その根拠として、「世界各国の人達が集まる国際的なスポーツとかを見てると、みんな英語話してるけどそれぞれ母国語寄りのイントネーションが強いです。F1が好きでよく見てますけど、イタリア人スペイン人フィンランド人…それぞれ個性的な発音で喋ってます」と、具体的なグローバルスタンダード(=多様な訛り英語の共存)を提示しています。
この意見は、「要は話し手の伝えたい内容を、しっかりと話せるかどうかがポイント。『すごく努力されたのだな』とあるが、高市総理は立派だよ」というコメントにも通じます。「経験では豪州とシンガポールでも発音はかなり違うので、要は話し手の伝えたい内容を、しっかりと話せるかどうかがポイント」であり、「ネイティブと同じである必要は全くない」という主張は、多くの共感を集めました。
6-4. 人柄とコミュニケーション力への評価
最後に、高市氏の英語力を、彼女自身の「人柄」と結びつけて評価する声も見られました。
「決して流暢な英語ではなかったですが、各国首脳と挨拶している映像を拝見しました。英語は必ずしも上手くないけど天然のコミュ力や人柄でカバーされてらっしゃるのだと思います」というコメントです。
これは、須賀川氏が指摘した「delivery」にも通じるものです。言語そのものの能力が不足していたとしても、笑顔やアイコンタクト、堂々とした態度といった非言語的なコミュニケーション(天然のコミュ力)や、相手に好感を持たせる「人柄」が、その技術的な欠点を補って余りある、という評価です。高市氏のスピーチが、ジョセフ・クラフト氏に「好感が持てる」と評されたのも、この点が大きかったのかもしれません。
これらのネット上の反応を総合すると、日本の世論は、高市氏の英語の「流暢さ」には多くを期待していない一方で、その「努力する姿勢」や「伝えようとする意志(ド根性)」、そして「堂々とした態度」を強く支持していることが鮮明に浮かび上がってきます。
7. まとめ:高市早苗の英語力と、私たちが学ぶべきこと
本記事で多角的に検証してきた、高市早苗総理の英語力に関する議論は、単なる一政治家のスキル評価を超え、日本の国際社会におけるコミュニケーションのあり方を問うものとなりました。最後に、その要点を改めて総括します。
高市早苗の英語力 総括
-
英語力は「凄い」のか?
技術的な流暢さ(ペラペラ)という意味では「凄い」レベルではありません。専門家からも「うまくない」「ペラペラではない」と指摘されています。しかし、物怖じしない「姿勢」や、過去からの「努力の跡」は高く評価されています。 -
どのくらい話せる?
「実務的な場面対応型」です。ASEAN会議のような準備されたスピーチは英語で対応可能ですが、ひろゆき氏の質問のような即興の質疑応答は、リスクを避けて日本語を優先する傾向があります。 -
話せる理由はなぜ?
最大の理由は、20代の「米国連邦議会フェロー」としての実務経験です。留学ではなく、ワシントンの政治の現場で、政策文書の読解やレポート作成といった「実務英語」を鍛え上げたことが基盤となっています。 -
ひろゆき氏への回答は?
「英語で回答して」という要求に対し、“Japan is back.” という象徴的な英語ワンフレーズのみで対応。即興の英語議論には乗らず、本論は得意な日本語に引き戻すという、極めて戦略的な「危機管理能力」を見せました。 -
総理の英語力は重要?
必須ではありませんが、外交上「強い武器(加点要素)」となります。特に首脳間の非公式な信頼関係構築に役立ちます。歴代総理では岸田氏、安倍氏、麻生氏らがその能力を発揮してきました。 -
ネット上の反応は?
「発音がネイティブでない」ことへの批判は少数派でした。むしろ、「努力する姿勢」「伝える意志(ド根性)」「訛りは関係ない」といった、彼女の態度やコミュニケーションの本質を評価する肯定的な意見が多数を占めました。
高市早苗氏の英語力を巡る一連の現象は、私たち日本人自身の「英語コンプレックス」を映し出す鏡のようなものでした。
私たちはあまりにも長く、「ネイティブのような完璧な発音でなければ、英語を話してはいけない」という見えない呪縛に囚われてきたのかもしれません。しかし、ネット上の多くの声援が示したように、大切なのは発音の美しさではなく、相手の目を見て、自分の言葉で、必死に「伝えよう」とする意志、すなわち「delivery」です。
高市氏の(専門家曰く)「うまくない」かもしれないが「堂々とした」スピーチの姿は、期せずして、「完璧な英語」の呪縛から私たちを解き放ち、「伝える勇気」こそが重要であると、身をもって示してくれたのではないでしょうか。
彼女の「ド根性英語」が、トランプ氏に似ていると評されたように、今後、世界の多様なリーダーたちとどのような化学反応を起こしていくのか。その「伝える力」の真価は、これからの外交の舞台でこそ問われていくことになります。