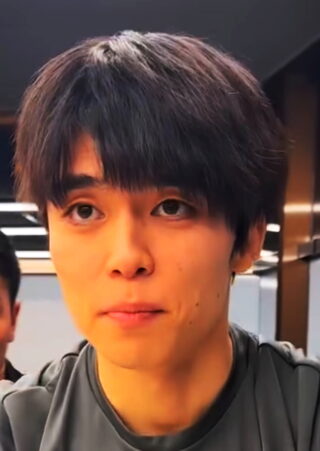2025年11月2日、私たちの生活に直結するガソリン価格について、大きな動きがありました。
ガソリン税に上乗せされ続けてきた「暫定税率」(1リットルあたり約25円)が、とうとう2025年12月31日をもって廃止されることで与野党6党が正式合意したのです。
物価高に苦しむ多くの国民にとって朗報かと思いきや、この決定に河野太郎(こうの たろう)元外相が待ったをかけました。
「フェラーリやポルシェに入れるガソリンを下げる必要はないのでは」という発言が、今、大きな議論を呼んでいます。
この発言の真意はどこにあるのでしょうか。
また、暫定税率の廃止で地方の財政は本当に大丈夫なのでしょうか。
この記事では、河野氏の発言が炎上している理由、国民や地方からの様々な声、そして発足したばかりの高市早苗(たかいち さなえ)新政権が直面する財源問題について、詳しく掘り下げていきます。
河野太郎氏「高級車発言」炎上の概要(何があった?)
発端となったのは、2025年11月2日に放送されたTBS系「サンデー・ジャポン」での河野太郎氏の発言です。
ガソリン暫定税率の廃止についてコメントを求められた河野氏は、まず「僕はずっと石破内閣の頃から反対だったんです」と、一貫して反対の立場であることを明言しました。
その理由として、地球温暖化問題への懸念を挙げた上で、次のように述べたのです。
「本当に困っている人にはガソリンだったり、電気だったり支援をするけれども、フェラーリやポルシェに入れるガソリンを下げる必要はないのでは」
この「高級車」を引き合いに出した発言が、物価高に直面する多くの国民の感覚とズレているのではないかと、インターネット上などで大きな反響を呼び、批判的な意見が相次いでいます。
河野氏がガソリン暫定税率廃止に反対する理由とは?
河野氏がなぜこれほどまでに暫定税率の廃止に反対するのか、その主張を整理してみましょう。
理由1:地球温暖化対策への懸念
河野氏は、「今年の夏は日本も42度になった」と近年の異常気象に触れ、地球温暖化が深刻化していると指摘しました。
その状況下でガソリン税を下げることは、社会に対して「化石燃料を普通に使っていいんだよ」という誤ったメッセージを送ることになり、非常にまずいと懸念を示しています。
理由2:富裕層優遇への疑問とピンポイント支援の主張
これが今回最も注目された「高級車発言」の核心です。
河野氏の論理は、税金を一律で下げることは、フェラーリやポルシェといった高級車に乗る富裕層をも利することになる、というものです。
そうではなく、本当に生活に困窮している人々に絞って、ガソリン代や電気代をピンポイントで支援するべきだと主張しました。
さらに、その財源を燃費の良い車やEV(電気自動車)への買い替え補助金に回した方が、将来的なガソリン使用量が減り、価格高騰の影響も少なくなるという代替案を提示しています。
理由3:根本原因は「円安」であるという指摘
河野氏は、物価高対策としての減税そのものにも疑問を呈します。
「いま、原油の値段が下がっているのに円安で高くなっているわけだから」と述べ、問題の根本は円安にあると指摘しました。
物価高対策というのであれば、政府と日本銀行が連携し、日銀は金利を引き上げ、政府は財政再建に取り組むべきだと主張します。
小手先の減税策は、それ自体がインフレ(物価上昇)の原因になりかねないとして、根本的な経済政策の転換を求めています。
炎上した河野氏発言へのネット上の反応と世間の声まとめ
河野太郎氏のこれらの主張、特に「高級車」発言に対して、SNSやニュースサイトのコメント欄では、賛否両論、特に批判的な意見が数多く寄せられています。
「論点ずらしだ」という批判的な意見
最も多く見られたのが、「論点がズレている」という厳しい指摘です。
- 「フェラーリやポルシェに乗っている国民がどれだけいるのか。ごく一部の富裕層を引き合いに出すのはおかしい」
- 「大多数の国民は物価高で苦しんでいる。高級車に乗らない多くの国民を助けるためにやることに意味がある」
- 「議員は高額な歳費や文書交通費をもらっている。まず自分たちの支援を見直すべきだ」
といった声が上がっています。
特に地方在住者とみられる人々からは、「地方にとって車は生活必需品。通勤、病院、買い物に軽自動車を使っている人が大半だ」「都会人の感覚では分からないだろう」といった、生活実感に基づいた反論が目立ちました。
また、軽油価格が下がることで物流コストが抑えられ、結果的に諸物価を下げる効果を期待する声もありました。
「それなら別の税制で対応すべき」という提言
一方で、河野氏の「富裕層優遇」という視点自体は理解できるとしつつも、対策が違うのではないか、という提言も多く見られました。
- 「富裕層のことが気になるなら、ガソリン税ではなく所得税や金融所得税で適切に負担を求めればよい」
- 「庶民の生活が苦しいのだから、海外のように食料品の消費税を軽減・廃止する方が先だ」
- 「法人税も、中小企業は据え置き、大企業の税率を上げるなど、他にやるべきことがある」
このように、ガソリンという生活必需品で調整するのではなく、税制全体で公平性を担保すべきだという意見です。
「暫定税率」のあり方への疑問
そもそも「暫定税率」という制度そのものへの根強い不信感も浮き彫りになりました。
- 「暫定税率は1974年に道路整備の財源として導入されたもの。温暖化対策のために導入された税ではない」
- 「“暫定”と言いながら50年も続いてきた。ガソリン税に消費税がかかる二重課税状態でもあり、この矛盾を廃止するのは当然だ」
河野氏が廃止の反対理由に「環境」を持ち出したことに対し、制度の成り立ちから考えてお門違いだ、という指摘も見受けられました。
河野氏の主張に一部理解を示す声
少数ながら、河野氏の主張に一定の理解を示す声もありました。
- 「環境問題への視点や、富裕層に恩恵が行くという指摘は半分当たっている」
- 「EVへの買い替え支援は必要」
ただし、そのEV支援についても、「ガソリン税を払っていないEVがなぜ支援されるのか」「むしろ道路維持費として『バッテリー税』を課すべきだ」「雪国ではEVは実用的ではない」といった、さらなる反論も寄せられています。
ガソリン暫定税率廃止でどうなる?地方自治体への影響
国民生活の負担軽減が期待される暫定税率の廃止ですが、手放しでは喜べない深刻な問題も抱えています。それは地方自治体の財源です。
福岡県の服部誠太郎(はっとり せいたろう)知事は、2025年10月31日の定例記者会見で、この問題に強い懸念を示しました。
福岡県の試算によると、ガソリン暫定税率の廃止(11億円減)に加え、軽油引取税の廃止も実現した場合(198億円減)、県の税収は合計で約209億円も減少する見込みだというのです。
このうち約66億円は、県内の市町村に交付されている財源です。
服部知事は、「地方自治体は独自財源が非常に少なく、(減収すると)新規事業が考えにくくなる」と述べ、財政運営に支障が出かねないと訴えました。
その上で、国に対し「恒久的な代替の財源措置が講じられるべきだ」と強く要請しています。
浮上する代替財源の議論 高市新政権の課題とは?
暫定税率の廃止によって全国で失われる税収は、軽油と合わせて約1兆5000億円と試算されています。この巨大な財源の穴埋めは、発足したばかりの高市早苗(たかいち さなえ)新政権にとって待ったなしの課題です。
2025年11月1日放送のカンテレ「ドっとコネクト」では、元自民党衆院議員の杉村太蔵(すぎむら たいぞう)氏が、この財源についての私案を披露しました。
杉村氏が提案したのは、好調なインバウンド(訪日外国人旅行者)に着目した「入国税」です。
政府が目標とする年間6000万人の訪日客から、1人あたり2万5000円を徴収すれば、単純計算で1.5兆円が確保できるという試算です。「円安の今なら高く感じないはず」とも主張しましたが、これには共演者から「実は政府はもう検討しています」と指摘され、ズッコケる一幕もありました。
このように代替財源の確保が急務となる中、高市新政権の経済政策そのものが大きな岐路に立たされています。
高市新政権の「積極財政」と「財政再建」の壁
高市早苗首相は、「安倍3.0」とも呼ばれる積極的な財政出動による経済成長を目指しています。
その証拠に、財務相には旧大蔵省出身で積極財政派とされる片山さつき(かたやま さつき)氏を起用。この人事に財務省内では「ゴジラが来たかのような驚き」が広がったとも報じられています。
しかし、政権が取り組むべき課題は山積みです。
今回のガソリン減税(1.5兆円の減収)に加え、防衛費の増額(2兆円以上)、高校授業料の無償化(6000億円以上の支出増)、さらに日本維新の会との合意事項である大阪副首都構想(4兆~8兆円支出増)など、巨額の財源を必要とする政策が並びます。
皮肉なことに、アベノミクスの「生みの親」である浜田宏一(はまだ こういち)氏からは、「今は円安・インフレが問題だ」として、高市氏の志向とは真逆の「金融引き締め」への転換を求める声が上がっています。
浜田氏は、河野氏と同様に「インフレの際に補助金やガソリン減税を行うのは逆効果」と、減税策を厳しく批判しています。
「最強の味方」麻生太郎氏が壁になる可能性
さらに、高市首相の政権誕生を支えた「最強の味方」が、最大の壁になる可能性も指摘されています。
高市氏の後見人とされる麻生太郎(あそう たろう)副総裁です。
麻生氏は財務相を長く務め、消費税増税を実現させた人物であり、その本質は「財政再建派」とされています。
麻生氏の義弟である鈴木俊一(すずき しゅんいち)氏が幹事長に就任し、官邸の秘書官にも財務省のエース級や麻生氏に近い人物が配置されたことで、高市首相の「積極財政派」と、麻生・鈴木両氏を中心とする「財政再建派」による暗闘がすでに始まっているとの見方も出ています。
まとめ
2025年12月末に迫ったガソリン暫定税率の廃止。
これは、物価高に苦しむ多くの国民、特に車を生活必需品とする地方の人々にとって、切実な願いが反映された決定です。
一方で、河野太郎氏が指摘するように、地球環境への配慮や、富裕層への恩恵といった論点も無視はできません。
そして何より、地方自治体の貴重な財源が失われるという現実的な問題が迫っています。
高市新政権は、国民の生活負担の軽減、インフレ対策、財政再建、そして環境問題という、時に相反する複雑な課題を同時に解決しなければなりません。
「高級車」発言をきっかけに噴出した国民の多様な声を、新政権がどう受け止め、1.5兆円という財源問題にどう答えを出していくのか。その手腕が厳しく問われています。